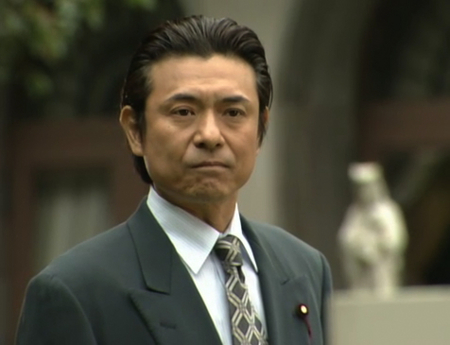1. 『仮面ライダー』第84話「危うしライダー!イソギンジャガーの地獄罠」(1972年11月4日放送)
「平成仮面ライダー」シリーズなどでメガホンを取った映画監督の長石多可男さんが先月31日、進行性核上性麻痺のため都内の病院で亡くなっていたことがわかった。享年68歳。東映が3日に発表した。
長石監督は1945年1月7日生まれで、広島県江田島市出身。1971年から『仮面ライダー』に助監督として携り、監督として2000年の『仮面ライダークウガ』以降、『仮面ライダー剣(ブレイド)』『仮面ライダー電王』など平成ライダーシリーズを手掛けた。遺作はVシネマ『帰ってきた天装戦隊ゴセイジャー last epic』。(編集部・入倉功一) 「シネマトゥデイ」2013年4月3日
120本のライダーと180本のスーパー戦隊を手がけた巨星が逝った。記事にある「映画監督」という点からいうと、小林靖子の劇場映画デビュー作『劇場版 仮面ライダー電王 俺、誕生!』(2007年)が、監督にとっては(興行収入13億8千万円と、キャリア中最大のヒット作になったが)最後の劇場公開作品になってしまった。われわれ年輩のファンには、初代『仮面ライダー』時代の逸話も忘れられない。特に脚本を担当した第11話と、監督補を担当した第84話。
第11話「吸血怪人ゲバコンドル」(1971年6月11日)は、いわば急場しのぎの作品であった。シリーズ撮影開始後わずか10話で主演の藤岡弘(現:藤岡弘、)がバイク事故で転倒、重傷を負うアクシデントが起こり、苦肉の策として「本郷の旧友の、FBI特命捜査官の滝和也」(千葉治郎/現:矢吹二朗)という狂言廻しを出すことになった。たぶんものすごい突貫工事だったんだろうけど、その脚本執筆をまかされたのが助監督の長石さんだった。過去の撮影素材から「大学の研究室で顕微鏡をのぞく本郷猛」「バイクで疾走する本郷猛」といったカットを流用し、残る本編は滝和也のドラマで動かし、変身後のライダー姿の代役によるアクションでなんとかしのぐ、という、大人になって鑑賞すると味わい深い一編である。ちなみに2号ライダー、一文字隼人の登場は第14話からであるが、FBIの滝和也も、以降もレギュラーキャラクターとしてシリーズに定着することとなる。
一方、第84話「危うしライダー!イソギンジャガーの地獄罠」(1972年11月4日)は、原作者、石森章太郎(後の石ノ森章太郎)が脚本・監督を担当した一編である。石森先生といえば大の映画好きで、漫画家として大成した後も「映画監督をやってみたい」と公言されていた。それでおそらく制作サイドから「それなら一度ライダーの監督をやってみませんか?」と持ちかけたのではないかと推測する。つまり大ヒット作の功労者に対する一種のご接待である。
であるから石森先生に失礼があってはならない。そこで、現場の経験がない先生のサポート役をつとめたのが長石多可男である。なのでこの回だけは助監督ではなく「監督補」という特別なクレジットになっている。
この回は「接待回」だけあって、たしか通常の二本分の予算をつぎ込んでいるんじゃなかったかな。冒頭の空撮からクライマックスまで、終始ヘリコプターが出て来たり、爆発シーンも気合いが入っていたり、何かと特別だった。しかし、それに負けず劣らず印象的だったのが、原作の魅力を活写したビジュアルである。
原作版『仮面ライダー』には円を使った効果線がけっこう多い。ひょっとすると当時、円を正確に描ける製図用品でも買ったところだったので使いまくったのかなぁ、とか、石森プロに正確に同心円を描けるアシスタントがいたのかな、なんてバカな邪推をしたくなるほどだ。
たとえば冒頭、レースにそなえ、バイクでタイムトライアルをしていた本郷は、黒塗りの車に急襲され、気がつけばショッカーの改造手術台の上にいる。このとき、途中で意識を失う本郷の記憶の連鎖は「襲われたバイクの、空しく回るバイクの前輪」が「ショッカーの改造手術台を照らす照明の光輪」へとオーバーラップすることで表現される。
あるいは、バイクに乗った敵が本郷を襲う時には、コンパスで描いたような正円で(実際コンパスで描いているのだが)ヒーローの周りをぐるぐる回る。
これに類する表現はけっこうあった。
こういう意匠が、第84話でもわりときっちり出て来る。立花のおやっさんが全国の少年ライダー隊に指令を飛ばす。出動する少年ライダー隊員の自転車の前輪にカメラが寄ると、それが本郷猛のバイクの前輪にオーバーラップする。
ショッカーの戦闘員たちがバイクに乗ってやってくる。すると当然のように彼らは、本郷をぐるぐる取り巻きにする。
またイソギンジャガーと仮面ライダーが海岸で対決する望遠シーンも、まさに石森漫画の実写版という感じ。
具体的に挙げろって言われても即答できないが、こういう場面は石森先生の作品でしばしば見かけた気がする(『サイボーグ009』の誕生篇で、海中での戦闘を終えて出てくる009の場面なんか、海岸線のロングショットだったように記憶していたが、改めて確認したら違っていた)。
長石多可男は助監督時代に、こうやって、石森章太郎のイメージを忠実に実写映像化する、という、けっこう難しそうな課題をクリアしていた。面白いのは、このときに見せた構図とか、あるいは望遠レンズの多用といった技法のいくつかのなかに、後年の長石監督作品の映像的な特徴が早くも現れている点だ。長石多可男がすでに映像作家としての個性を確立していた証左とも言えるが、見方を変えると、石森章太郎監督の補佐というチャンスに、普段できない技法もいろいろ試した結果、その幾つかが後に長石作品の特徴となっていった、という側面もあるのかも知れない。
2. セーラームーン・電王・シンケンジャー
こんな話をしていてはキリがない。今回とりあげようと思ったのは、小林靖子が脚本を手がけた『侍戦隊シンケンジャー』の第34話「親心娘心」(2009年10月18日OA)である。
この作品は、長らく仮面ライダーのローテーションを担ってきた長石監督が、1999年の『救急戦隊ゴーゴーファイブ』以来、およそ10年ぶりにスーパー戦隊に帰って来た記念すべき作品であった。だけどもう10年も経っている。シンケンジャーの現場を切り盛りする監督たちは、パイロット版が中澤祥次郎で、あと諸田敏とか竹本昇とか渡辺勝也とか、要するに長石チルドレンみたいな人たちばかりだ。そこへ「お父さん」が降臨して来たわけであるから、現場はたいへんな騒動だったらしい。この作品で初めてチーフとなった宇都宮孝明プロデューサーは、その楽しい混乱ぶりを公式ホームページに次のように描いている。
長石監督が10年振りに戦隊シリーズを撮ってくれるということで、スタッフ一同お祭り騒ぎ。小林靖子さんが「今年一番緊張する本打ちです」と呟き、松村カメラマンが「俺が撮らなきゃな」と笑みをうかべ、佛田特撮監督が「スペシャルサービス!」をしてくれました。そしてそして、「この時を待ってました」と想定外の行動を起こした男が一人…なんと、渡辺勝也監督が助監督(監督補)を志願。「立場を考えなさい」という長石監督の説教も、「あなたローテーション監督なんですけど…」という私の説得もまったく聞く耳持たず。「お願いですからやらせて下さい」と、『ファイブマン』以来の師弟コンビを強引に再現、大泉中を驚愕させました。(中略)長石・渡辺、師弟コンビ再結成を聞きつけて…「僕がセカンドやりますわ〜」(by竹本)、「じゃあ僕がカチンコ打ちます」(by中澤)今、シンケンジャーの監督ローテーションは深刻な危機を迎えております。
会社でもなんでも、上司がこれだけ慕われている現場なら、良い仕事ができないはずはないよなぁ。
実写版セーラームーンのファンの視点から言うと、同じ小林靖子が脚本を書いた『仮面ライダー電王』(2007年)と『侍戦隊シンケンジャー』(2009年)は、セーラームーン(2003年)のリメイクというか、かなりダイレクトな発展型に見える。たとえば実写版セーラームーンのモチーフのひとつは多重人格テーマだった。ただ、前半を引っ張った亜美とダークマーキュリーの人格分裂の物語はともかく、後半のうさぎとプリンセス・ムーンの物語は、やや消化不良気味で終わってしまった。これに対して『仮面ライダー電王』は、同じ多重人格テーマを「イマジンたちに憑依されて人格の変わる良太郎」というポップな形で表現し直して、より洗練された結末まで物語を導くことに成功している。
またセーラームーンは「前世からの使命を受けながら、因習を捨て、今を生きるために戦うプリンセスと護衛戦士たちの物語」であるが、シンケンジャーも「先祖代々の使命を受けながら、因習を捨て、今を生きるために戦う殿様と侍戦士たちの物語」である。「前世よりも今を生きる」というテーマは、武内直子の原作セーラームーンでも、前世の母クイーン・セレニティの口から語られていた。小林靖子はこの方向をさらに過激に進めて、前世というものに対してほぼ完全に否定的な態度をとっている。ただ一方で、アニメ時代のセーラームーンが「前世から結ばれた恋」というロマンティックな要素によって人気を獲得していたことも確かで、セーラームーンの実写版である以上、そういう側面を無視しきれなかったというか、そのへんの齟齬が最後まで解消されきれなかったように思う。なにしろあの大ヒットしたアニメのセーラームーンの実写版である。小林靖子が、自分自身の作家としてのモチーフをこの作品につぎ込もうと思っても、おのずと制約があった。だから続く『電王』と『シンケンジャー』でリマッチを果たしたのだと、私は思っている。
話をシンケンジャーに絞ると、たとえば「影武者」というモチーフに、セーラームーンの明らかな発展形態を見ることができる。
原作のセーラームーンでは、ヴィーナスは敵の目を欺き、本物のプリンセスをかくまう使命を担った影武者で、本物のプリンセスは、セーラームーンとして戦士のなかに紛れこんでいる。
でも考えてみると、影武者のセーラーVが姿を隠していて、敵の攻撃から守るために隠しておかなくちゃならないプリンセスが、戦士のリーダーとして危険な最前線に放り出されている、っていう状況は如何なものか。プリンセスに強くなってもらうため、という大義はあるが、しかしこれ本末転倒なのではないだろうか。でももちろん、ドラマとして考えた場合、セーラームーンを戦いの場に参加させないことには、物語は先へ進みようもない。
ならば逆に、セーラームーンの方を「プリンセスの影武者」にしてしまえばいいじゃん。というところから小林先生は「主役で殿様のレッドが実は影武者」という、シンケンジャー終盤の大どんでん返しを思いついたのである(推定、というか邪推)。
だけどそのせいで、シンケンレッドこと志葉丈瑠(松坂桃李)は、殿様としてみんなの命を預かっちゃったけど、オレ本当は影武者だし、こんな大ウソついて良いんだろうかという呵責に苦しむこととなった。その悩める心境を描いたエピソードが第12幕「史上初超合体」だ。
一方、実写版のAct.12も、ヴィーナスが、私プリンセスの影武者なんかやってて良いんだろうか、と悩む話だ。まあこっちは、本物のプリンセスがあまりにバカだったので、私はこんなバカのために命を張っているのか、と意気消沈してしまうわけで、だいぶシンケンジャーとは趣が違うが、まあ同じ12話で「影武者の苦悩」がテーマになるというのも、なんとなく不思議な符合である。という話はすでにした。(ここ)。
3. 『美少女戦士セーラームン』Act.34(長石監督作品ではありませんが)
だいぶ前置きが長くなったが、長石多可男が久々にスーパー戦隊の監督となったシンケンジャー第34話「親心娘心」も、実は実写版セーラームーンAct.34とモロにかぶるのだ。Act.34は、亜美とママ、レイとパパという、2組の親子の感情のもつれがテーマとなる話だ。レイの場合、Act.8で、政治家で忙しかった父の手で神社に預けられたこと、Act.10で、幼くして母をなくしたことが語られていて、それらの伏線がこのエピソードで畳まれる、大事な回である。レイのなかでずっと「政治の仕事に熱心で、死んだママも残された私も見捨てた、怖くて冷酷な男」だったパパ、火野隆司(升毅)のイメージが、みるみる「妻や娘に対する愛情表現の仕方が分からないだけの不器用なお父さん」に変わっていくクライマックスは、娘のレイが北川景子ということもあって、およそ娘をもつ父親ならば、涙なしには見られない名場面です(よね)。
レ イ「どうして、どうしてあの日、病院に来なかったの?」
隆 司「しつこいなお前は、何か理由があれば許せるのか?」
レ イ「理由によるわ」
隆 司「仕事だ。本当に忙しかった。お前を預けなければならなかった理由も、ほかに無い」
レ イ「じゃあ…」
隆 司「分かれとは言わん」
隆 司「レイ、取材があるんだ。親子で食事をする。出席しなさい」
レ イ「たぶん、もう少し時間が経ったら…」
隆 司「…そうか」
4. 『侍戦隊シンケンジャー』第34話「親心娘心」(2009年10月18日放送)
一方、シンケンジャー第34話。シンケンピンク、白石茉子(高梨臨)は、最初っからレッドを殿様あつかいしないで「丈瑠」と呼んで、仲間の戦士からも姐さん呼ばわりされるような、強くて気丈なアネゴ肌。一方で、弱いものを見ると庇護しないではおれない保護者性を発揮して、仲間の戦士が落ち込んでいる時など、手料理で励ましてあげようとする家庭的な一面も。実際、同じ女性戦士であるイエローには「何でかな… どうしてか思っちゃうんだよね。普通のお嫁さんになって普通のお母さんになりたいなって…」と将来の夢を語っている。
でも、この人の手料理はかなり危険である。包丁がうまく使えないので、戦いに使うシンケン丸という剣でカボチャを切る。当然ながらまな板まで切れてしまう
味付けもなかなか壮絶らしく、食べれば松坂桃李もノックアウトである。
このあたりの描写がただの息抜きギャグではないことが分かるのが第34話だ。彼女もレイやまことと同じように、幼い頃から母の温もりを知らずに育って来た。古風な家庭の女の子だったら、料理のイロハくらい、母に教わっていそうなものだが、そんな手ほどきも受けていないので炊事のたぐいはからきしダメ。そのへんを痛いほど自覚していたからこそ、「普通のお母さんになりたい」という夢を抱いていたわけですね。
ただ彼女の場合、母親は死別したわけではなくて、車椅子での生活にはなったが、ハワイで元気に生きている。そして父親はレイのパパみたいに、見た目が怖そうな人でもない。ていうかナンパっぽい。シンケンジャーは先祖代々受け継がれるものだが、先代のシンケンピンクですらない。先代は母親なのである。そういうお父さん、白石衛(富家規政)がとつぜんシンケンジャーたちの前に現れるところから、第34話は始まる。
衛 「茉子、久しぶりだなぁ。元気だったか。こんなにきれいになって」
衛 「失礼、私、茉子の父親の白石衛です」
千 明「えっ?」
ことは「そしたら、前のシンケンピンクさんですか?」
衛 「えっ、まさかぁはははは。前のシンケンピンクは私の妻。つまり茉子の母親です。私は侍でも何でもありません。しがない婿養子です」
茉 子「お父さん!」
衛 「やっと声が聞けた」
茉 子「どうしたの、急に」
衛 「お前を迎えにきたんだ、茉子。シンケンジャーやめて一緒にハワイに行こう」
茉子「えっ?」
茉子の母親は、敵との激しい戦いで傷ついた心身を癒すために、ハワイで療養することになり、父はそれに付き添って海を渡った。しかしまだ戦いが終わったわけではないので、娘の茉子だけは、次世代のシンケンピンクとなるべく日本に残され、祖母のもとで侍の教育をうけることになった。
えーと、エピソードとしては、このあと小学校の子どもたちが敵に大量に拉致されて、心配で居ても立ってもいられない親たち、という物語があるんですけれど、だいぶ長くなっちゃったので、話は飛ばしてクライマックス、私が実写版セーラームーンAct.34のリメイクだと思うシーンまで一気に飛んじゃいますね、悪いですけど。
子どもたちがかくまわれている場所を突き止め、戦いを挑むシンケンジャー。そこになぜか茉子のお父さんが飛び込んでくるんだが、案の定とばっちりを食って負傷してしまう。それでも茉子を追う白石衛。
衛 「茉子、大丈夫か?」
茉 子「お父さん、どうしてこんなところまで」
衛 「待て、茉子」
茉 子「放っとけるわけないでしょ。助けなきゃ」
衛 「ああっ!」
茉 子「お父さん何とも思わないの?子供を心配している人たちのことだって見てたでしょ。同じ親じゃない!」
衛 「そうだ。親だよ、親なんだ。自分の子どもを安全な場所に避難させたいと思う、身勝手な親だ。茉子、それはお母さんも同じなんだよ」
茉 子「そんなこと……」
茉 子「だったらどうして……あのとき……私も一緒に……」
茉 子「置いていかれたと思った。最後までお母さん、私のことなんか目に入らなくて、だからずっと独りで侍になるために……今になってどうして……」
衛 「連れて行きたかったよ、お前も……だが、お母さんは最後の戦いで心も身体もひどく傷ついていたんだ。自分のことだけで精一杯だった。お父さんも、侍になるお前を手放さないおばあさんから、とても引き離す余裕が……」
衛 「言い訳だな。お前をひどく傷つけた。恨むのは当然だ」
衛 「茉子……」
茉 子「私、侍はやめない。お父さんたちのことを恨んでいるわけじゃないし、後悔もしていないから」
茉 子「ただ……あの時……ただ……」
セーラームーンのAct.34の場合、レイと父親が話している教会の墓地と、戦士たちが妖魔と戦っている場は、だいぶ離れている印象があって、だから父娘の会話の場面の「静」と、アクションの「動」は、よく言えば対比がクッキリしていたし、悪く言えばちょっと分離し過ぎていた。
でもこのシンケンジャー第34幕は、両親共に健在なのに置いていかれてしまったという、ある意味レイよりも複雑な過去をもつ茉子の葛藤と激情が、目の前に敵との戦いを見据えながら描かれている。その結果、画面の中では静と動がめまぐるしく入れ替わり、表現される内容はセーラームーンより複雑になっている。けれども、言葉にできない様々な想いを叩きつけるかのような最後の立ち回りが、実にカッコよく決まっているために、単純明快な娯楽作品としてのビジュアルの完成度はシンケンジャーの方が高い。脚本が進化しているせいもあるだろうが、やはりアクションとエモーションが渾然一体となったこういう演出は、長石多可男あってこそ、という気がする。弗田洋も、長石監督作品だということで、なで切りにされて爆発する敵たちのビジュアルを特にびしっと極めているように感じる。人徳である。
長石多可男監督は、実写版セーラームーンが放送されていた2003年10月から2004年9月の間に『仮面ライダー555』を4本、『仮面ライダー剣』を10本も撮っている。残念ながらセーラームーンの方にご出向いただくことは出来なかったが、もしAct.48やFinal Actを長石監督が演出されていたら、と夢想せずにはいられませんね。頑張ってくださった鈴村監督や舞原監督には申し訳ないが、もうひとまわり大きな、「星のハメツ」の危機にふさわしいスケール感のある最終回になっていたのではないだろうか。訃報を聞いてから『仮面ライダー電王』の最終3話を改めて鑑賞して、つくづくそう思った。合掌。
長石監督の『電王』最終回についても改めていろいろ思うところがあったが、それはまた機会があったらということで。